世界を知れば、世界は変えられる
映画『哀れなるものたち』をTOHOシネマズで鑑賞しました。
1週間早く先行上映をやっていたようで、少し早く観ることができました。
監督は『ロブスター』『聖なる鹿殺し』『女王陛下のお気に入り』のヨルゴス・ランティモス。
出演者は『女王陛下のお気に入り』で監督とタッグを組んだエマ・ストーンの他、ウィリム・デフォー、マーク・ラファロ。

ヨルゴス・ランティモスの作品を観たことがある方はお察しいただけるかと思いますが、なかなか強烈な作品でした。私はかなり好きです。

あらすじはこんな感じだよ👇
天才外科医によって蘇った若き女性ベラは、未知なる世界を知るため、大陸横断の冒険に出る。時代の偏見から解き放たれ、平等と解放を知ったベラは驚くべき成長を遂げる。
https://www.searchlightpictures.jp/movies/poorthings
今回の記事では、『哀れなるものたち』の感想と解説をお伝えしていきます。
ネタバレを含んだ内容になりますので、未鑑賞の方はご注意を。
観終わった後の疑問の回収や、一回の鑑賞で楽しみ切りたい方はぜひご一読ください。
人生讃歌の映画!

『哀れなるものたち』は、人生の素晴らしさや生きることの楽しさを描いた人生讃歌です。
主人公ベラ(エマ・ストーン)は、囲われた生活から抜け出し、様々なものを体験します。
誰かの歌声やエッグタルト、痴話喧嘩やSEX、音に合わせて踊る楽しさ…。
全てが新しくって刺激的。純粋にこれらを経験し、味わいます。
大人になったらこれらの刺激に対して鈍麻してしまい、楽しみ切れなくなっているんだなということを突き付けられました。
しかし、世の中は楽しいだけじゃない。貧困に苦しむ人もいるし、自分だってお金がなければ身を削って働かなければならない。
そういった、世界の辛い側面もベラは知ることになるんです。
辛いことも知った上で、世界をよくしようという思いを膨らませていくんですね。
幼い頃キレイな心でもって、大きなことをしようとか、何者かになってやろうといった情熱。
これらを思い出させてくれる素晴らしい作品です。
また、終盤のセリフ、
「生は魅惑的だから許せる。噓と狡猾な罠は許せない」
にもグッときました。
本当に感動する作品ですよ。
『フランケンシュタイン』と『ファニー・ヒル』の融合
本作は、ウィリム・デフォー演じるバクスター博士が、脳移植でベラを生み出す物語です。
これって、『フランケンシュタイン』によく似ているんですよね。
映画評論家の町山智浩さんも、Xでこのように呟いています。
私も『フランケンシュタイン』はすぐにピンときたんですが、『ファニー・ヒル』については知りませんでした。
著者はイギリスの作家、ジョン・クレランドで、発行されたのは1748年。
調べてみたところ、『ファニー・ヒル』はこんなお話だそうです。
ファニー・ヒルという名の登場人物をめぐる物語である。彼女は貧しい田舎娘で、貧困のために故郷を離れて街へ出ることを余儀なくされる。都会で騙された彼女は売春宿で働かされることになるが、処女を失う前に、恋に落ちたチャールズという男と連れ立って売春宿を逃げ出す。同棲をはじめて数ヵ月後、チャールズは突然父親によって国外へ送り出されることとなり、ファニーは都会で生き延びるために次の恋人を探さざるをえなくなる。彼女は売春宿でセックスの手ほどきを受け、搾取されているという自覚は持ちながらも後悔することはない。その上、ファニーは悪女としても振舞ってみせる。娼婦としての彼女は、最低でも貴族階級の裕福な男たちの前にしか姿を現さない。
Wikipediaより引用
なるほど、確かに売春宿で働くという点がそっくりですね。
また、ベラが「女性が男性を選ぶべきだ」というセリフも、この小説からきているのかもしれません。
エマ・ストーンがすごい!

『ラ・ラ・ランド』『スパイダーマン』など、世間的な知名度の高いエマ・ストーン。
本作はかなり攻めた役を演じています。
赤ん坊のような話し方や歩き方、座り方はとてもチャーミングなんですが、強烈なのはS〇Xのシーンです。
惜しげもなく、何度も素っ裸のシーンが出てきます。
これだけでも、この映画は伝説級です…。
しかし、それらのシーンもまた、人間としての喜びを魅せるシーンですので、背徳感やうしろめたさを感じることはありません。

熱烈ジャンプという形容が、めちゃくちゃ爽やかで印象的でした笑
エマ・ストーンは製作も担っているので、嫌々という訳でもないでしょうしね。
同世代のスターであるマーゴット・ロビーは、『バビロン』でフルヌードはありませんでしたので、何だか気合の差を見せられたような気もします。
R18版ジブリ
本作を私はR18版ジブリだと解釈しました。
ジブリ自体が実は子どもよりも大人向けであるということは、これまで当サイトで何度も語っていますので、あえて大人版ではなく、R18版と形容させていただきます。
もう少し詳しく述べると、宮崎駿監督作品ですね。
宮崎駿監督作品に、一貫していることは『生きろ』を伝えていることです。
『魔女の宅急便』では、思春期ならではの辛さを描き、
『もののけ姫』や『風の谷のナウシカ』では文明社会の危うさを描き、
『風立ちぬ』では戦時中の混沌描いています。
世の中には汚いものや不条理がたくさんあるけれど、そんな中でも自分らしく使命をもって生きなさいということを伝えているんですね。
そして最新作『君たちはどう生きるか』は宮崎駿監督が自身をよりストレートに投影してそれを私たちに伝えてくれました。
『哀れなるものたち』もまた、主人公ベラが喜びや快楽とともに、世の不条理や文明社会の汚さも知ります。
それを経験して、知った上で、より良くしようと生きていく。
ジブリ作品はどちらかというと、「仕方がないけど生きていく」というネガティブさに寄っていますので、『哀れなるものたち』のほうが前向きな作品だと思います。
白黒からカラーへ
本作は白黒から始まります。
あるシーンを機に、カラーになるんです。
この、カラーに変わるタイミングが、秀逸なんですよ。
ベラが旅立つ時、つまり、自由になる時、本作には色がつきます。
これもまた、人生に色どりをつけるというか、様々なことを知っていくというのを、視覚的にも伝えるうまい仕掛けだなと思いました。
原題『Poor Things』の意味
本作の原題は『Poor Things』です。
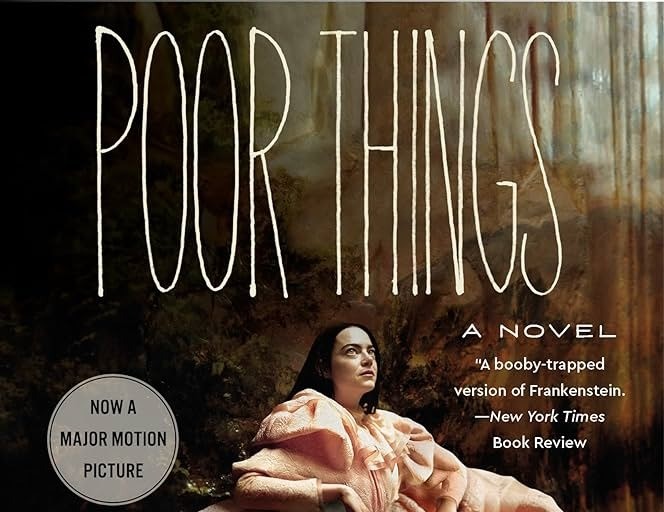
日本ではそのまま直訳して『哀れなるものたち』になっていますね。
「もの」っていうのは、「物」なのか「者」なのか。
「Things」は「事」という訳もありますね。
ベラが旅に出て、世の中にあふれている物や、出来事の愚かさや哀れさを知るというのが、タイトルの意味なのでしょう。
劇中では、ベラ自身に向けて博士から「哀れな子」と言われるシーンもありました。
また、ベラとの旅の中で、マーク・ラファロ演じるダンカンも、自身の愚かさに気づいていきます。
だから複数形の「Things」になっているんでしょうね。
『シャイニング』の登場人物にそっくり
スタンリー・キューブリック監督のホラー作品『シャイニング』。
『哀れなるものたち』には、『シャイニング』に登場する重要なキャラのディック・ハロランとそっくりな人物が登場します。

それは、キャサリン・ハンター演じる、売春宿の女主人。
『シャイニング』のハロランは、不思議な力「シャイニング」を持つ人で、同様に「シャイニング」をもつ少年ダニーの指南役のような立ち位置のキャラクターです。
で、『哀れなるものたち』の女主人もベラも不思議な力は持ってないんですが、この女主人は売春宿や俗世を生き抜く知恵のようなものをベラに指南してくれる存在。
何となく顔とか表情も似ている気がします笑
『聖なる鹿殺し』を観れば、ランティモス監督が、キューブリック監督のファンであることは間違いないと思いますので、この説も少なからずあるんじゃないかと思います。
今日の映学
最後までお読みいただきありがとうございます!
映画『哀れなるものたち』の感想と見どころをお伝えしました。

生きることの素晴らしさや喜びを再認識できる、素晴らしい映画です。

エマ・ストーンのガッツあふれる演技にも注目だよ!
X(旧Twitter)はこちら
https://twitter.com/bit0tabi
Instagramはこちら
https://www.instagram.com/bit0tabi/
Facebookはこちら
https://www.facebook.com/bit0tabi/
noteはこちら
https://note.com/bit0tabi


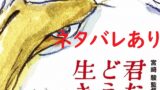




コメント