海外の映画を観た後に邦画を観ると、どこか映像が「つるっとしていて、深みがない」と感じることはありませんか?
この違和感の正体について、映画評論家の間でもよく語られるのが「日本の現場で使っているカメラが安いからだ」という説です。
実際のところ、これはあながち間違いではありません。ただ、話はそれだけに留まらず、そこには「見せ方の制約」や「制作思想の差」といった、日本映画界が抱える根深い事情が複雑に絡み合っています。

カメラだけの問題じゃないんだ。

そうなんだ。詳しく解説していくよ。
予算の差がもたらす物理的な限界
「カメラが安い」というのは、カメラ本体の価格に限った話ではありません。映画のルック(外観)を決定づける「撮影システム全体」への投資の差を指しています。
映像の質感を決めるのはカメラ本体以上に「レンズ」です。海外では驚くほどの価格の映画専用「シネレンズ」を贅沢に使いますが、予算の限られた日本の現場では、テレビドラマで使われる汎用レンズや、放送用機材を流用せざるを得ないケースが多々あります。また、重厚な空気感を作るための照明機材や、ダイナミックな動きを支える特機(クレーンやレール)に予算を割けないことも、結果として「平板で、どこか物足りない画」を生んでしまう一因となっています。
そして予算を割けない要因として深く関わっているのがキャスティングです。
「タレントファースト」なキャスティングの弊害
機材の制約と同じくらい大きな理由が、日本特有のキャスティング事情による「見せ方のルール」です。
日本の商業映画の多くは、出演しているタレントやアイドルの顔を隅々まで明るく、美しく見せることが最優先されます。事務所サイドの意向もあり、影を極力排除した「フラットなライティング」が選ばれがちです。かつての日本映画界では、照明監督が絶対的な権限を持ち、女優たちも「いかに印象的に撮ってもらえるか」と彼らに敬意を払っていました。しかし現在は、映画としての演出よりも「タレントのプロモーション」としての側面が強くなり、照明がそのための作業にトーンダウンしてしまった面は否めません。

個人的に、豪華キャスト勢ぞろい系の映画は、キャスティングに予算がかかり過ぎているのでは?という思いが膨らんでしまいます…。増えれば増えるほどスケジュールも難しくなって撮影時間も限られるし、高額の出演料で他に予算が回せない。みたいな。
ポストプロダクションに現れる思想の差
さらに、映像の仕上げ段階である「カラーグレーディング(色彩調整)」の工程でも大きな差が生まれます。
海外映画では、フィルムのような粒子感を加えたり、特定の色味を乗せて「非日常」を作り込みますが、日本の現場では現実感のあるクリアな発色を好む傾向にあります。あるいは、そこまで作り込む予算や時間が十分に確保できないことも多く、結果として「テレビで観慣れた映像」に近い質感に落ち着いてしまうのです。

そもそもドラマ作品の劇場版みたいなのが多いしね。
今日の映学:映像の質感は「業界構造」の現れ
最後までお読みいただきありがとうございます。
このように、「カメラシステム全体の予算不足」という物理的な制約に加え、「タレントを綺麗に見せる」という商業的な制約が組み合わさることで、今の日本映画特有の質感が形作られています。
映像のザラつきや陰影は、物語の深みを伝えるための大切な要素です。機材の制約を乗り越え、あるいはあえて「見せない」美学を追求するような、映画としてのルックに徹底的にこだわった作品が、日本の実写映画でもさらに増えていくことを期待したいですね。

そういう意味で、豪華キャストを使用していない作品にも注目してみてほしいんです。

確かに。日本映画の見方や選び方が変わってきそうだね。
X(旧Twitter)はこちら
https://twitter.com/bit0tabi
Instagramはこちら
https://www.instagram.com/bit0tabi/
Facebookはこちら
https://www.facebook.com/bit0tabi/
noteはこちら
https://note.com/bit0tabi
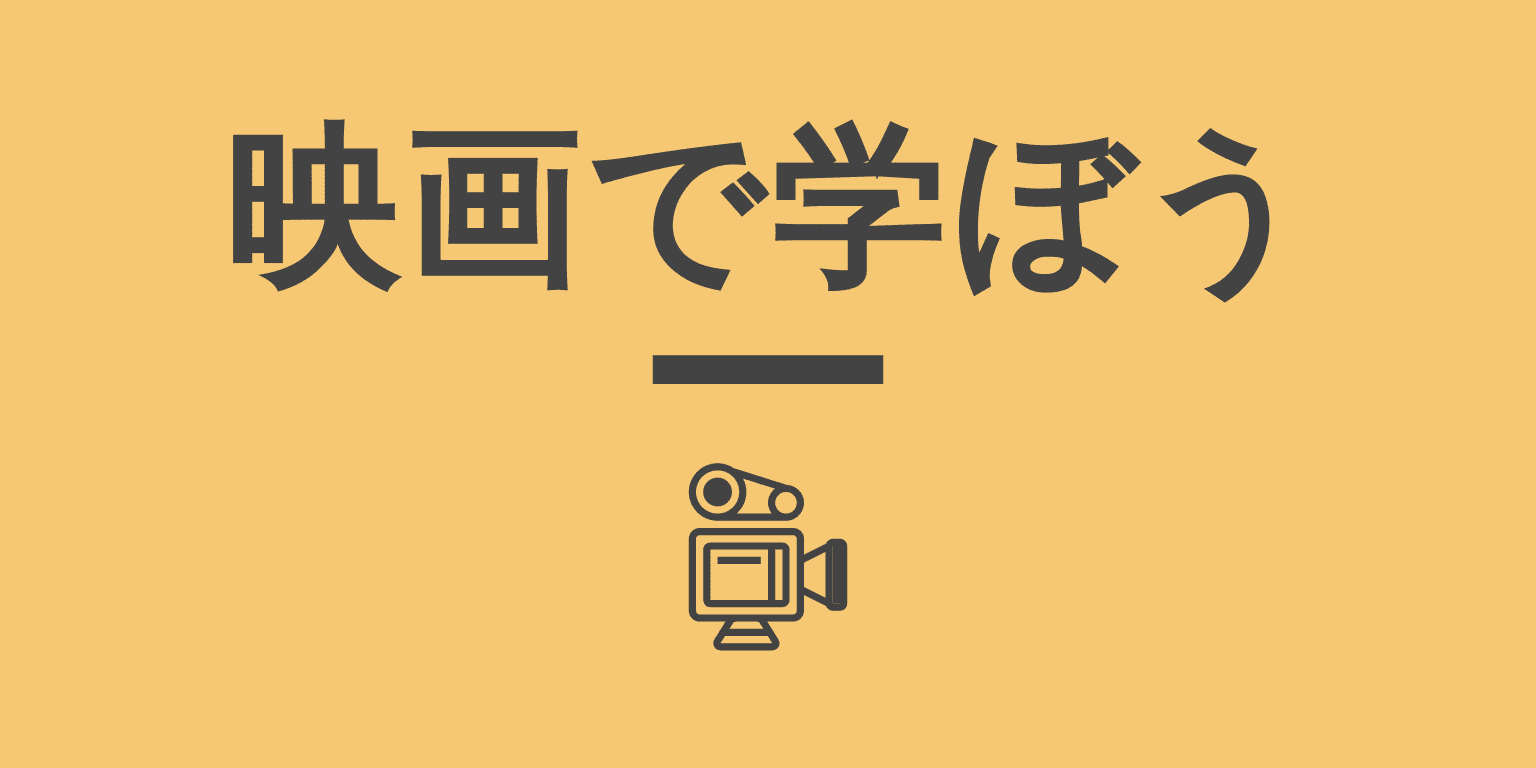


コメント