Netflixで独占配信されているドキュメンタリー『パーフェクト・ネイバー:正当防衛法はどこへ向かうのか』を視聴しました。2023年にフロリダ州で起きた、白人女性が隣人の黒人女性を射殺した実在の事件を追った作品です。

一見、アメリカの閑静な住宅街で起きた隣人トラブルに見えますが、その背景には日本人には想像しがたい法律の壁と、人間の深淵な闇が潜んでいました。

えぇ、法律の壁ってどんなの?

生活にしても法律にしてもかなり日本とはギャップを感じるよ。詳しく解説していこう。
「自分の領域」という妄執と曖昧な境界線
アメリカの郊外では、家々の間にフェンスがない「オープン・フロントヤード」が多く見られます。日本人から見れば広々とした美しい景観ですが、この「境界線の曖昧さ」こそが本作においては悲劇の火種となりました。

加害者のスーザン・ロリンツにとって、子供たちが自分の敷地だと思い込んでいた場所で遊ぶことは、迷惑を超えた「聖域への侵犯」だったようです。
実際には、そこは厳密には彼女の私有地ではありませんでしたが、彼女の頭の中では一歩でも近づく者はすべて「侵入者」として定義されていました。
そしてとうとう、子どもが置き忘れたタブレットを巡る些細な口論が、最悪の結末を招いてしまったのです。

三つの「境界線」が引き裂いたもの
本作を観終わって深く考えさせられるのは、加害者が自分の殻を守るために引き続けてしまった、三つの「境界線(ライン)」の存在です。
物理的な境界線:美しい芝生に引かれた「一線」 アメリカの住宅街に広がる、フェンスのない美しい芝生。本来は開放的なはずのその場所で、彼女は「ここからは自分の聖域だ」という目に見えない線をあまりにも強固に引きすぎていました。実際には共有地であった場所さえも自分の支配下にあると思い込み、そこを無邪気に走る子供たちの足音を「攻撃」と捉えてしまった。その物理的な執着が、悲劇の始まりでした。
心理的な境界線:「完璧な市民」という名の孤独と断絶 ロリンツは自分を「法を守る善良な市民」と定義し、そこから外れる隣人を「理解できない他者」として切り離していました。偏見や孤立によって築かれたこの心理的な壁は、隣り合って暮らす人間同士の対話を拒絶し、最後には「相手を消し去るべき敵」として映し出してしまったのです。
法的な境界線:「身を守る権利」という名の盾 そして最も残酷なのが、彼女が自らの行為を正当化するために利用した「法の境界線」です。彼女が銃の引き金を引くことを後押ししてしまった「スタンド・ユア・グラウンド(Stand Your Ground / 立ち去る義務なし)」法。

次項で詳しく解説していきます。
あまりに危うい「スタンド・ユア・グラウンド法」
本作の核となるのが、フロリダ州を含むアメリカの多くの州で採用されている「スタンド・ユア・グラウンド(Stand Your Ground / 立ち去る義務なし)」法です。

日本の法律では、正当防衛が認められるためには「他に逃げる道がないか」「反撃の程度は妥当か」が厳格に問われます。しかし、この法律は「脅威を感じた場所から逃げる必要はなく、命の危険を感じればその場で致死的な力(銃撃など)で行使してよい」というものです。
さらに恐ろしいのは、その判断基準が極めて「主観的」である点です。
- 相手が武器を持っていなくても、自分が「殺されるかもしれない」と主観的に思えば成立しうる。
- 鍵のかかったドア越しであっても、「ドアを壊して入ってくると思った」と言えば防衛線として認められる可能性がある。
この法律の存在が、ロリンツに「ドア越しに、武器も持たない母親を撃つ」という暴挙を「正当な防衛」だと言い張らせる後ろ盾となってしまいました。本来、命を守るための最後の砦であるはずの法律が、個人の妄執を守るための凶器へとすり替わってしまったのです。

スーザン・ロリンツは最終的に裁判官や裁判員に過剰防衛であると判決されました。結局のところ、法で認められていようが、その裁量は個々の常識や判断に委ねれられるといったところでしょう。
【豆知識】映像から見えるアメリカと日本のギャップ
本編の筋道とは直接関係ありませんが、日本人読者が映像を観ていて「これはどういうこと?」と気になりそうなポイントをいくつか補足します。
- 警察署内を歩く「ボーダー服の女性」の正体 劇中、警察署の廊下で緑と白のボーダー服を着た女性が掃除をしているシーンが一瞬映ります。実は彼女、本物の受刑者(囚人)です。アメリカの地方の警察署では、素行の良い受刑者が「信託囚」として署内の清掃作業などに従事することがあります。署内に囚人が普通に存在している光景は、日米の文化の違いを象徴する一幕です。
- 手錠をかけるまでの「長い対話」 警察官がロリンツの言い分を長時間聞いているのは、単に丁寧なのではなく、後の裁判で「本人がどう供述したか」という証拠を残すため、あえて自由に喋らせているという捜査上の側面もあります。
- 黒人コミュニティの強固な結束(Black Solidarity) 終盤、事件解決を求めて多くの人々が結集するシーンは圧巻です。アメリカの黒人コミュニティにとって、こうした不当な暴力に対する連帯は、自分たちの命を守り、司法を動かすための極めて重要な文化です。一家族の悲劇として終わらせず、社会全体の問題として可視化させるこのエネルギーは、個人の権利が強調されがちなアメリカにおいて、もう一つの強力な「支え」となっていることがわかります。

今日の映学
最後までお読みいただきありがとうございます。
本作は警察のボディカメラ映像や監視カメラの記録で構成されており、そこには演出ではない「生々しい現実」が映っています。
警察官になだめられてもなお、自分の権利を主張し続けるロリンツの姿には、考えさせられるものがあります。
「身を守る権利」は大切ですが、それが他者を排除する免罪符になってはならない。私たちは誰しも、誰かの隣人であり、同時に誰かにとっての「不完全な隣人」になり得るのだということを、この映画は静かに突きつけてきます。

法と個人の価値観、そして土地の境界線の曖昧さ。じっくり考えさせられる映画でした。

ご近所にとって自分がどんな存在なのか。あんまり考えたこともなかったよ。
X(旧Twitter)はこちら
https://twitter.com/bit0tabi
Instagramはこちら
https://www.instagram.com/bit0tabi/
Facebookはこちら
https://www.facebook.com/bit0tabi/
noteはこちら
https://note.com/bit0tabi
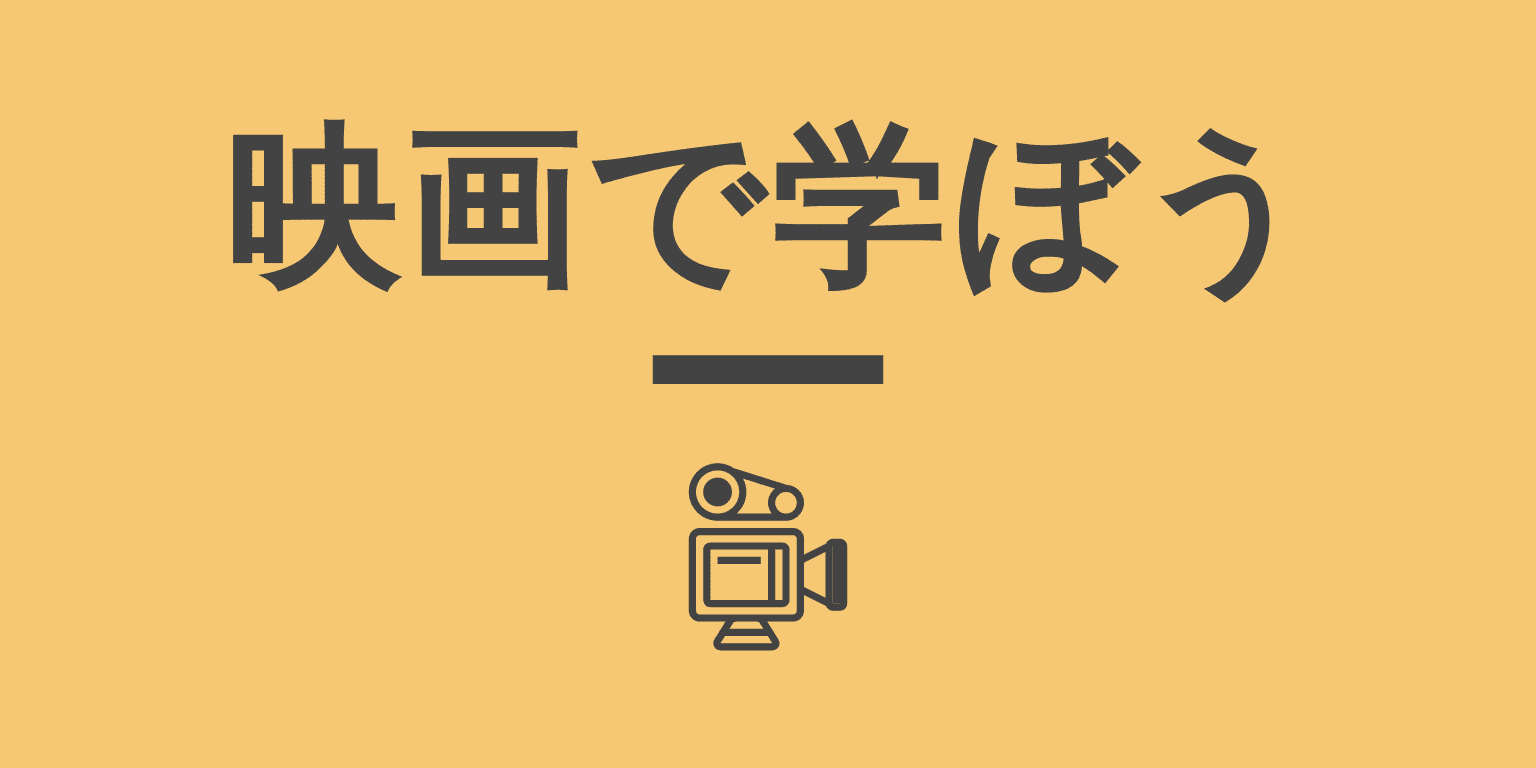



コメント