イングマール・ベルイマン監督が1966年に発表した『ペルソナ』。
心理ドラマという枠を超え、映画というメディアの可能性そのものを根底から問い直した、極めて挑戦的な作品です。
その大胆な手法と深いテーマ性は、デヴィッド・リンチの『マルホランド・ドライブ』やドゥニ・ヴィルヌーヴの『複製された男』といった現代の名作にも影響を与え、今日に至るまで映画を志す者たちの必修科目となっています。

今観ても衝撃を受けますよ。今まで観てきた映画の源流はここにあったか。という感じ。

特に『ファイトクラブ』ね!
1. 映画の構造そのものへの挑戦:革新的な「メタ演出」
『ペルソナ』は、観客が「映画を見ている」という事実を徹底的に意識させるメタ演出に満ちています。
- 「第四の壁」の破壊: 演劇や映画には、舞台と観客を隔てる見えない壁である「第四の壁」が存在します。ベルイマンは、この壁を何度も壊すことで、観客を物語の外部に引きずり出しました。
- 映画の物理的側面: 映写機の光、フィルムの燃焼、映像の乱れといった、映画が「作り物」であることを示す演出は、観客に「これはフィクションである」という事実を突きつけ、映画の存在そのものへの考察を促します。

2. 鑑賞者に解読を促す「サブリミナル映像」の先駆性
『ペルソナ』の革新性は、その映像表現にも顕著に現れています。特に冒頭のモンタージュに一瞬だけ差し込まれる性的な映像は、ショックを与えるだけでなく、観客に能動的な解読を促すための重要な「ヒント」として機能しています。

具体的には、男性器つまり「チン」が映ります。
- 多層的な仕掛け: ベルイマンは、この映像を無意識と意識の両方に作用させることを意図していたのでしょう。最初は観客に不穏な感覚を植え付け、物語が進むにつれてそれがアルマの抱える性的トラウマや罪悪感、エリザベートの母性拒否といった、核心的な要素を読み解く鍵となるのです。
- テーマの象徴: この映像は、死体や蜘蛛といったイメージと並列されることで、生と死、そして性的な衝動やタブーといった、これから描かれる物語の根源的なテーマを暗示しています。この手法は、『ファイト・クラブ』におけるタイラー・ダーデンのサブリミナル的な挿入に、見事に受け継がれています。

3. アイデンティティの探求:人物の同化がもたらす心理的深み
『ペルソナ』は、女優エリザベートと看護師アルマという二人の女性のアイデンティティが溶け合っていく物語を通して、人間の「自己」の不確かさを探求しています。
- 鏡像としての関係性: 終始沈黙するエリザベートは、アルマの告白を引き出す「鏡」となり、やがて二人の顔がオーバーラップする有名なショットは、アイデンティティの境界線が消失したことを象徴しています。
- 後世への影響: この「他者との同化」というテーマは、自己の葛藤をドッペルゲンガーで描いた『複製された男』や、夢と現実の中で自己が分裂していく『マルホランド・ドライブ』といった作品に継承されました。社会的な役割(ペルソナ)に苦しむ人間が、自己の本質を見つけようとする物語の原型を、『ペルソナ』は築き上げたのです。

今日の映学
最後までお読みいただきありがとうございます。
『ペルソナ』は、優れた心理ドラマであるだけでなく、映画というメディアの限界に挑戦し、その表現の可能性を広げた「映画の教科書」のような存在です。
ベルイマンが示した大胆な手法と深いテーマ性は、今日に至るまで多くのクリエイターにインスピレーションを与え続けています。

その革新性と挑戦性こそが、『ペルソナ』を映画史における不朽の傑作たらしめているのですね。

偉大過ぎる!
X(旧Twitter)はこちら
https://twitter.com/bit0tabi
Instagramはこちら
https://www.instagram.com/bit0tabi/
Facebookはこちら
https://www.facebook.com/bit0tabi/
noteはこちら
https://note.com/bit0tabi


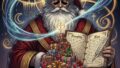

コメント