第98回アカデミー賞において、作品賞を含む4部門にノミネートされた『トレイン・ドリームズ』。デニス・ジョンソンの名作中編を映画化した本作は、決して派手なエンターテインメントではありません。
20世紀初頭、アイダホの深い山々で鉄道建設と森林伐採に明け暮れた一人の男、ロバート・グレイニアの数十年におよぶ孤独な人生の記録です。
しかし、なぜこの一見地味な男の生涯が、今これほどまでに私たちの心を揺さぶるのでしょうか。そこには、100年前のアメリカが抱えていた歪みと、現代の私たちが直面した「喪失の形」が、残酷なまでに重なり合っているからだと感じます。

時代背景や各シーンの考察をじっくりお届けします。

ネタバレありだから、気をつけてね!
歴史の歪みと「橋」という名の不条理
物語の主要な舞台となるのは1917年前後のアイダホ北部です。そこは、近代化の熱狂と、法が届かない野蛮さが同居する場所でした。冒頭、橋の建設現場で上海から来た労働者が無残に突き落とされるシーンは、当時のアメリカに蔓延していた凄まじい人種差別と、自警団的な暴力のリアルを突きつけてきます。
同じ移民でありながら、後から来た者を「敵」として排除する白人労働者たちの身勝手な論理。その不条理な光景を、グレイニアはただ困惑しながら見つめることしかできません。文明の象徴であるはずの「橋」が、実は誰かの犠牲の上に架けられているという事実は、開拓史の美談の裏側にある冷酷な真実を物語っています。
オスカー撮影賞も射程圏内、圧倒的な映像美
本作において特筆すべきは、今回のアカデミー賞で撮影賞の最有力候補とも目されている、その圧倒的な映像美です。アイダホの険しくも雄大な自然が、まるでその場の冷気や土の匂いまで伝わってくるかのような情緒的なタッチで捉えられています。
特に印象的なのは、光と影の使い分けです。鬱蒼とした森に差し込む一筋の光や、すべてを焼き尽くす火災の禍々しい赤、そして晩年のグレイニアを包み込む透き通った冬の光。それらは単なる背景ではなく、一人の人間の内面を映し出す鏡のように機能しています。大画面で観るべき、まさに「映画的な体験」と呼ぶにふさわしい映像の力が、この静かな物語に類稀なる緊張感を与えています。

記憶の淵に沈む異形:双頭の子牛と巨大魚
物語の冒頭、グレイニアの子供時代の回想シーンで、双頭の子牛や巨大魚がチラリと映し出されます。これらは、未開の地が持っていた最後の生命力の残り香であり、彼という人間を形作った根源的な風景です。
これらの異形のものたちは、開拓によって魔法や迷信が消えゆく中で取り残された世界の記憶であり、同時にグレイニアの人生に訪れる不可解で逃れられない運命を予感させる、不穏な装置として機能しています。

原作を読めば、より一層分かるかもしれません。
労働者の美学と、魂を削る仕事
映像の中で細部までこだわり抜かれたディテールも見逃せません。アメカジ好きの方なら、当時の労働者たちのスタイルにも目を奪われるはずです。シャンブレーシャツにベスト、泥にまみれたジーンズ、使い込まれたキャスケット。それらは過酷な自然に立ち向かう男たちの誇りと生活そのものです。
劇中、ウィリアム・H・メイシー演じる人物が放つ言葉が重く響きます。 「500年も生きる木を切り倒すのは、身体だけでなく魂も疲れる仕事だ」 自然を破壊することでしか文明を築けない人間の業、そしてその対価として削られていく労働者の精神。グレイニアが背負う孤独の背景には、こうした根源的な「痛み」が常に横たわっているのです。
「不在」という名の呪いと、コロナ禍の共鳴
物語の後半、グレイニアは耐え難い喪失を経験します。愛する妻と娘が火災に巻き込まれたとき、彼は仕事でその場にいなかったのです。
この「最期の瞬間に立ち会えなかった」という事実が、彼の人生に一生消えない影を落とします。悲劇の渦中にいなかったことで、彼は家族の死をどこか他人事のように、あるいは現実味のない白昼夢のように感じ続けてしまいます。
この感覚に、私は既視感を覚えずにはいられませんでした。パンデミックの最中、大切な人の死に目に立ち会えず、最期の別れすら満足にできなかった多くの人々がいます。私自身、当時地元を離れていて友人を亡くし、どこか実感が持てないまま取り残されたような感覚を抱き続けてきました。コロナ禍でなくとも、大切な存在の傍にいなかった経験が与える心のしこりは誰もが抱いているのではないでしょうか。グレイニアが抱える「実感のない喪失感」は、100年後の現在を生きる私たちが抱える痛みそのものなのです。

もしこの映画のこういった部分に共感できない人は、かなり幸せな人生を歩んでいると言えるでしょう。
ラスト考察:すべてが溶け合う瞬間の解放

ここはラストのネタバレあり!
最晩年のグレイニアは、飛行体験を通じて上下の感覚を失うほどの混乱の中に身を置きます。
なぜ彼は、その中で「すべてが繋がった」と感じたのでしょうか。
それは、彼が一生背負ってきた「人生の重み」や「後悔という名の重力」から、その瞬間だけ解放されたからではないかと私は考えます。
生死の境界も、過去と現在の区別も、すべてが曖昧になり世界に溶けていくような感覚の中で、彼はようやく自分の孤独な歩みを、宇宙の大きなうねりの一部として許せたのではないでしょうか。
今日の映学:私たちはみな、何かの「不在」を抱えて生きている
最後までお読みいただきありがとうございます。
映画の幕が下りた後、私たちはグレイニアが見た世界の広大さと、その圧倒的な静寂を忘れることができません。彼は英雄でもなければ、歴史に名を残す開拓者でもありませんでした。
しかし、彼がその生涯を通じて耐え抜いた孤独と、言葉にできなかった悲しみは、時を超えて今の私たちと地続きになっています。
大切な人を失ったとき、そこにいられなかった後悔。あるいは、移り変わる時代の波に取り残されていく不安。あるいは、抗えなかったことに対する罪の意識。それらは形を変えながら、今も私たちの日常の中に存在しています。
『トレイン・ドリームズ』が教えてくれるのは、どんなに不条理で孤独な人生であっても、いつか必ずそのすべてを肯定できる瞬間が訪れる、という静かな希望なのかもしれません。
かつてアイダホの地でグレイニアが感じた、あの境界線が消えるほどの解放感を、いつか私たちも自分自身の人生の果てに見つけられることを願って。

オスカーノミネート作品の中では、最もずっしりくるドラマでした。

Netflixでぜひ!
X(旧Twitter)はこちら
https://twitter.com/bit0tabi
Instagramはこちら
https://www.instagram.com/bit0tabi/
Facebookはこちら
https://www.facebook.com/bit0tabi/
noteはこちら
https://note.com/bit0tabi
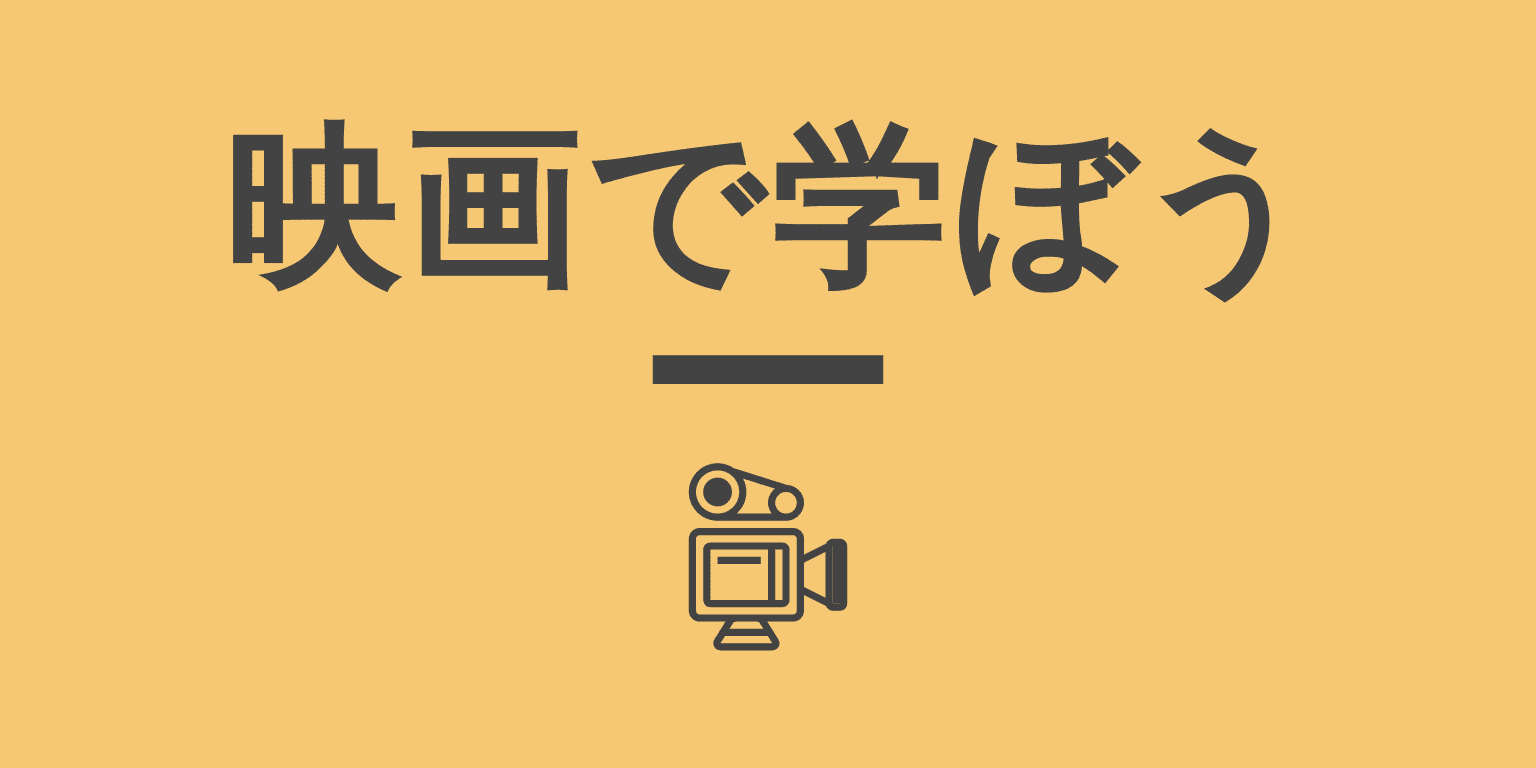


コメント