かつて長尺映画には当たり前のように存在したインターミッション(途中休憩)。
しかし、最近の映画館ではほとんど見かけなくなりました。
例えば、『風と共に去りぬ』や『ゴッドファーザー』のような往年の名作には休憩がありましたが、現代の『オッペンハイマー』や『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』といった長尺大作にはそれがありません。
また、近年は長尺の映画が多くなってきています。
それなのに、休憩はない。
おトイレや、集中力の問題で、ややしんどいのも事実。
一体どうして…

なんでなんだろう…。

この変化には、技術の進化、映画館側の事情、そして作り手の意図が深く関わっています。
かつてインターミッションがあった理由
昔の映画にインターミッションが設けられていた主な理由は以下の通りです。
- フィルム交換の必要性: 昔の映画はフィルムで上映されており、長尺作品は複数のリールに分かれていました。途中でリールを交換する時間が必要だったため、これが休憩として利用されました。
- 観客への配慮: 3時間を超えるような長尺作品では、観客の集中力維持やトイレ休憩といった身体的なニーズがありました。
- 興行上のメリット: 休憩時間中に売店での飲食物やグッズ販売を促進する機会でもありました。
インターミッションの時間は、一般的に5分から10分程度でした。
なぜインターミッションは消えたのか?
現代の映画からインターミッションが姿を消した背景には、主に以下の理由が挙げられます。
- デジタル上映への移行:
- 現在、映画のほとんどはデジタルプロジェクターで上映されるため、物理的なフィルム交換は不要になりました。これにより、技術的な理由で休憩を挟む必要がなくなりました。
- 興行側の効率性重視:
- 映画館、特にシネマコンプレックスは、スクリーンの回転率を上げて収益を最大化したいと考えています。インターミッションを挟むと、その分上映時間が長くなり、1日に上映できる回数が減ってしまいます。短い休憩時間でも、複数回の上映で大きな機会損失となるため、経営上避けられるようになりました。
- 作り手の「没入感」追求:
- 多くの映画監督や製作者は、観客を作品の世界に途切れることなく没入させたいと強く望んでいます。インターミッションによって、せっかく築き上げた集中力や物語の緊張感が途切れてしまうことを避けたいという意図があります。物語のテンポやリズムを維持するためにも、休憩は好まれません。
私はインターミッションが大好き
個人的に、私はインターミッションが大好きなんです。
『ゴッドファーザー』や『風と共に去りぬ』、『サウンドオブミュージック』は、リバイバル上映やDVD、配信サイトでもそのままインターミッションが残っていることが多いです。
そんな時は意気揚々と休憩しますね。家で観てても飛ばすことなく、ウキウキしながらトイレに行ったりドリンクを補充したりします。
あと、リバイバル上映だと、その合間でトイレに行きつつ、分からなかったシーンを調べることができるのもいいんですよね~。
スマホがある今の時代だからこそできる、お得な感じ。
また、当時の人々と同じ温度感を共有できるっていうのも、何だか嬉しくなっちゃいます。
今日の映学
最後までお読みいただきありがとうございます。
映画のインターミッションがなくなったのは、上映技術の進化、映画館の経営戦略、そして作り手の芸術的な追求が複合的に作用した結果です。
これにより、私たちは長尺の映画を途切れることなく一気に鑑賞できるようになった一方で、かつて映画鑑賞の一部だった「休憩時間」という体験は失われました。

個人的にはインターミッション大好きです。トイレ行けるし、集中続くし。リバイバル上映で残っている時はめちゃくちゃ嬉しくなります。

大作観てる!って感じもいいよね。
X(旧Twitter)はこちら
https://twitter.com/bit0tabi
Instagramはこちら
https://www.instagram.com/bit0tabi/
Facebookはこちら
https://www.facebook.com/bit0tabi/
noteはこちら
https://note.com/bit0tabi

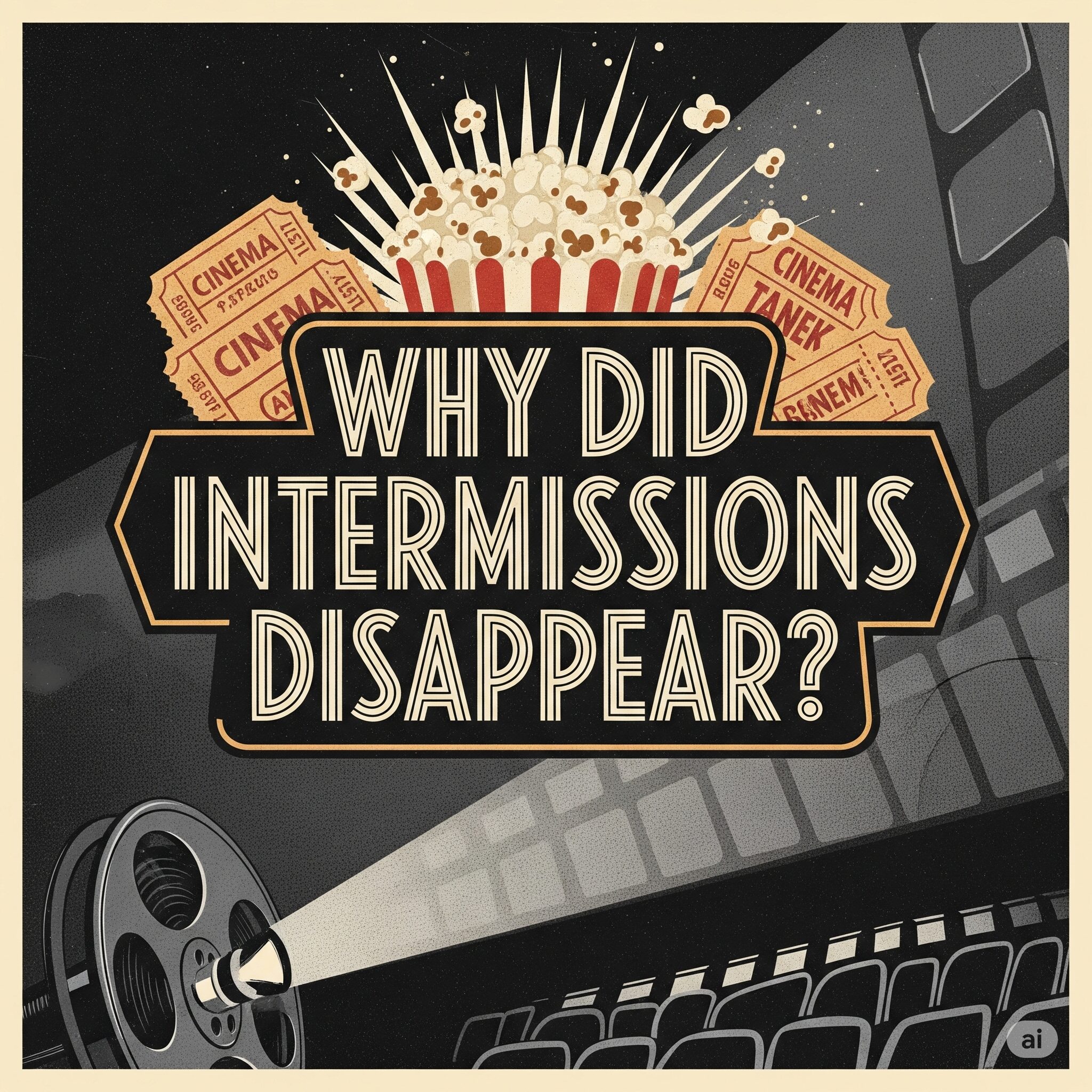



コメント