2025年は私にとって、生活の拠点がタイに移るという大きな変化の年でした。
環境が変われば映画の楽しみ方も変わるもので、今年は例年に比べると、映画館へ足を運ぶ回数が少なくなってしまったのが正直な反省点です。
タイの映画館で洋画を観る場合、基本的には「英語音声・タイ語字幕」というスタイルになります。
私は英語に関してはある程度理解できるものの、字幕なしで一言一句を完璧に聞き取れるほど堪能ではありません。
さらにタイ語は読めないため、劇中で語られている内容の理解度は、おそらく5割程度だったと思います。

それだとやっぱり楽しみにくいのかなぁ?

しかし、この「半分しか分からない」という状況が、思いがけない発見をもたらしてくれました。
文字を追わないことで解放される視線
日本で映画を観る際、私たちは無意識のうちに画面下部の字幕を追い、ストーリーを正確に把握しようと努めています。しかしタイの映画館では、私にとって字幕は機能しません。内容を理解しようと必死に耳を傾けつつも、視線は自然と画面全体へと向けられることになります。
そこで気づいたのは、字幕を追うという行為がいかに視覚的なリソースを占有していたか、ということでした。文字から解放された視線は、それまで見落としていた細部を捉え始めます。
この「視線の解放」を最も強く実感させてくれたのが、ポール・トーマス・アンダーソン監督の新作『ワン・バトル・アフター・アナザー』でした。
俳優の表情と画面の熱量
内容が5割しか分からないからこそ、私は映像そのものから情報を補完しようと、かつてないほど画面に集中しました。本作は「ビスタビジョン」という、非常に解像度と奥行きのあるフォーマットで撮影されています。その圧倒的な情報量に対し、字幕に邪魔されず真っ向から向き合えたのは、ある意味で贅沢な体験でした。
これまではストーリーを追うための補足として見ていた要素が、文字の介在しない世界では饒舌に物語を語りかけてきます。
ショーン・ペン演じる軍人ロックジョーの、瞳のわずかな揺れや、言葉に詰まる瞬間の喉の動き。あるいは、レオナルド・ディカプリオが見せる、追い詰められたジャンキーのような不安定な演技。背景に映り込む小道具の質感や、光と影が作り出す独特のコントラストにいたるまで、監督が1フレームごとに込めた意図をダイレクトに受け取ることができました。
それは物語を頭で「解読」するのではなく、映画という空間を身体で「体験」するような感覚です。言葉の壁があることで、かえって俳優の演技の機微や、映像美の熱量が鮮明に浮かび上がってきたのです。
今日の映学
最後までお読みいただきありがとうございます。
もちろん、緻密なプロットを楽しむには言葉の理解が不可欠です。
しかし、たとえ台詞が完璧に理解できなくても、優れた映画は映像と音だけで観客の感情を揺さぶる力を持っています。
タイの映画館の中で、言葉の壁を超えて伝わってくる感動に浸りながら、「映画とは本来、視覚芸術であった」という原点に立ち返ったような気がします。

日本に戻り、再び日本語字幕で映画を楽しめる環境になっても、この映像の細部に宿る熱量を逃さない視点は大切にしていきたい。

そう強く感じたなら、タイでの映画体験も貴重だったよね。
X(旧Twitter)はこちら
https://twitter.com/bit0tabi
Instagramはこちら
https://www.instagram.com/bit0tabi/
Facebookはこちら
https://www.facebook.com/bit0tabi/
noteはこちら
https://note.com/bit0tabi
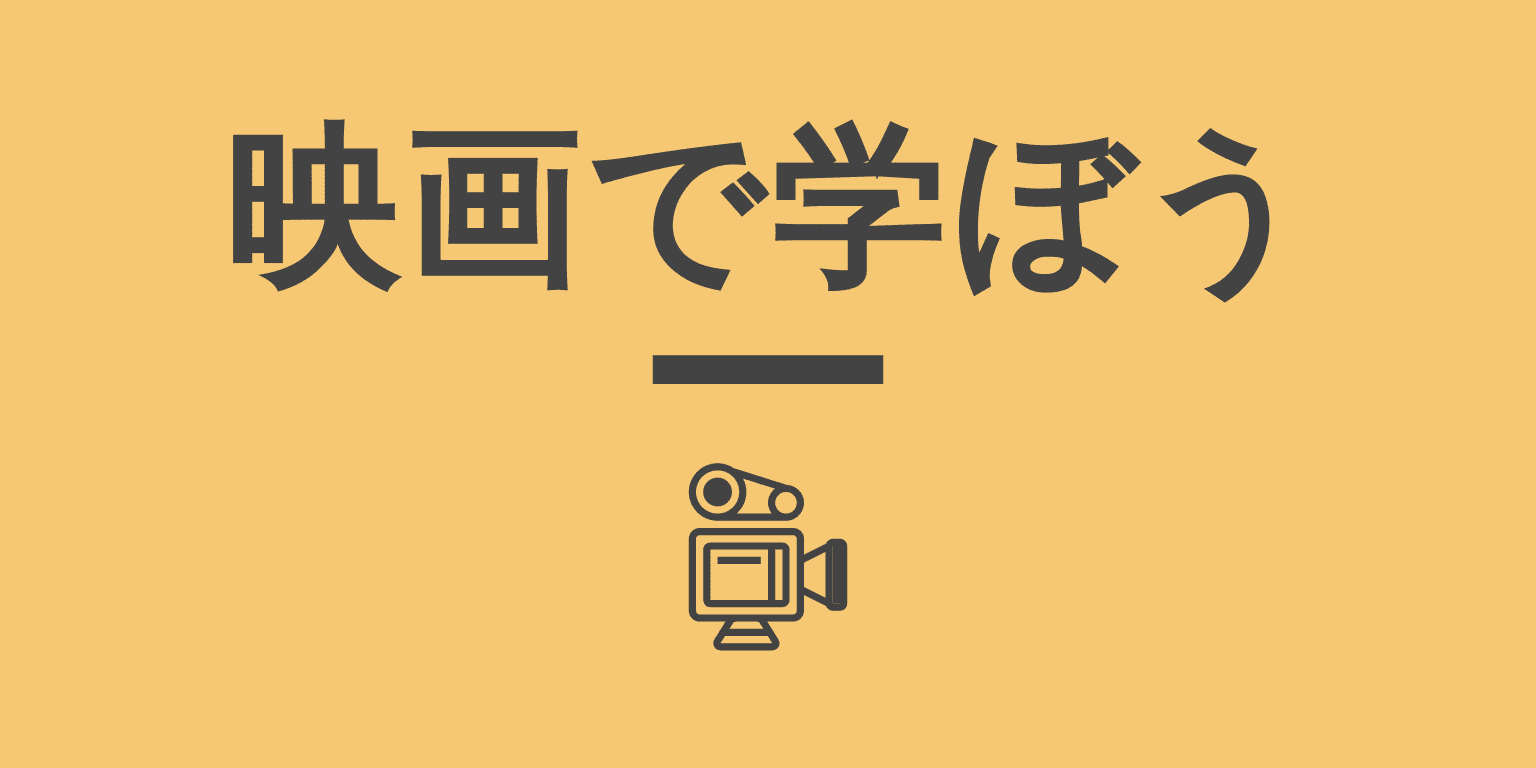




コメント