アリ・アスター監督の新作『エディントンへようこそ』は、私たちが数年前に経験したあの異常なパンデミック下を舞台にしています。
物語の冒頭、まず目を引くのはマスク着用を巡る緊迫感です。かつての現実世界でも、マスクをつけない者へのバッシングは凄まじいものがありました。
しかし、現在の視点からこの描写を振り返ると、また違った違和感が浮かび上がります。今ではむしろ、感染症が流行していても、頑なにマスクを外さない人々を冷ややかに見るような空気が一部で漂っています。
結局のところ、人々は科学的な根拠以上に、「その場の多数派に属していること」に酔い、そこから外れた者を排除することに正義を見出しているだけではないでしょうか。

『エディントンへようこそ』では、そのあたりの風刺を強く感じました。マジョリティの優越と、それ故に起こるマイノリティの陶酔感といいましょうか。

アリ・アスター監督らしい、斜めからの目線だね。
保安官という「地域の絶対者」
ホアキン・フェニックスが演じる保安官(Sheriff)という存在も、この物語を紐解く重要な鍵となります。アメリカの保安官は、私たちが想像する警察官(Police)とは少し立ち位置が異なります。彼らは住民の直接選挙によって選ばれる、いわば「民意の象徴」であり、その地域においては行政・司法を司る王のような独立性を持っています。
劇中の保安官が、公的なルールよりも「地域の空気」や「自身の裁量」を優先させる姿は、この独特の制度が背景にあります。彼自身が喘息を患っているという設定も、呼吸を制限されることへの恐怖と、社会的な強制力との間での葛藤をより際立たせています。
過剰な関心とカルトの相似形
本作では、白人の若者たちがBlack Lives Matter(BLM)といった人種差別問題に対して、どこか過剰なまでの関心を示す様子が描かれます。もちろん差別への抗議は正当なものですが、彼らの振る舞いにはどこか、自分たちが「正しい側」にいることを確認して安心したいという、自己愛的な陶酔が見え隠れします。
この「何かに盲信することで安心を得る」という心理は、混乱に乗じて勢力を拡大するカルト宗教の構図と驚くほど似通っています。アリ・アスター監督は、混乱期における若者たちの正義感を、ある種のカルト性を含んだ危ういものとして皮肉たっぷりに描いています。
1時間20分、暴走するコメディの真骨頂
映画が始まって約1時間20分が経過した頃、物語は決定的な転換点を迎えます。それまでのじわじわとした緊張感は、一気にバイオレンスな濁流へと姿を変えていきます。
前作『ボーはおそれている』がホラーの皮を被った内面的なコメディだったように、本作もまた、凄惨な暴力描写の中に救いようのない滑稽さが同居しています。
あまりに極端に振れ切った人間たちの行動は、恐怖を通り越して笑うしかありません。本作も、社会の歪みを笑い飛ばす「猛毒のコメディ」として捉えるのが、最もこの作品らしい鑑賞の仕方といえるでしょう。
今日の映学
最後までお読みいただきありがとうございます。
『エディントンへようこそ』は、パンデミックという極限状態において、いかに人間が「多数派の正義」に依存し、他者を排斥していくかを容赦なく描き出しました。

映画の中の出来事は決して遠い異国の寓話ではなく、私たちの日常のすぐ隣にある狂気なのかもしれません。

あなたもドキッとする場面があったんじゃないかな?
X(旧Twitter)はこちら
https://twitter.com/bit0tabi
Instagramはこちら
https://www.instagram.com/bit0tabi/
Facebookはこちら
https://www.facebook.com/bit0tabi/
noteはこちら
https://note.com/bit0tabi
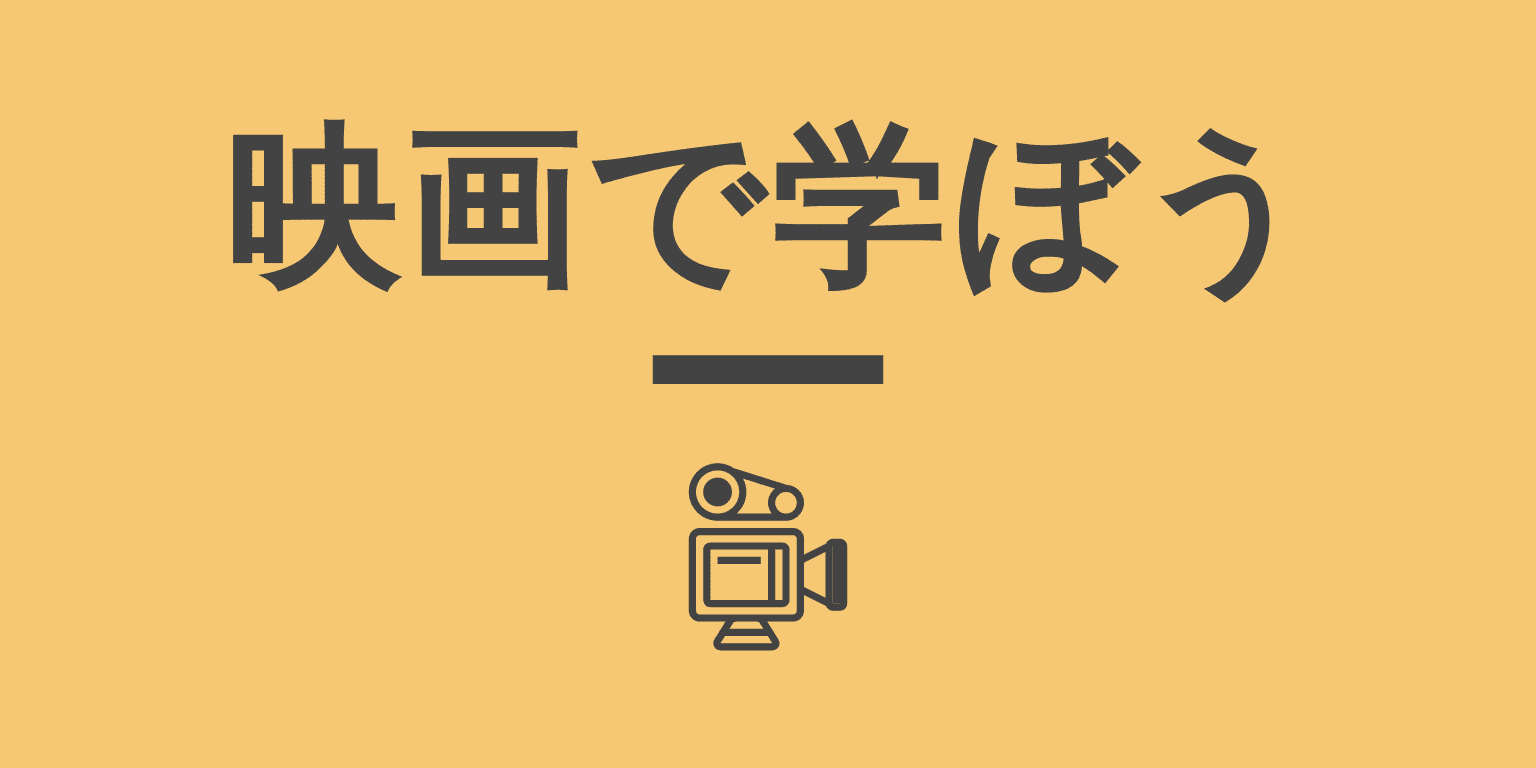



コメント